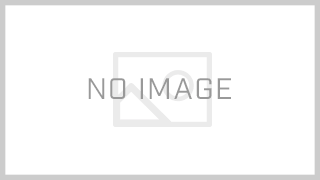撮影中は夜7時に就寝
Q普段、体調管理ではどんな事に気をつけていますか。
お酒が好きなので、以前は普段から結構な頻度で呑んでいました。でも『相棒』がシリーズになり始めた頃からは、撮影中は呑まなくなりました。もちろん二日酔いで撮影なんか出来ないし、若い頃のように無理も効かなくなっていますから。
いまは『相棒』の撮影に入ると一切呑みません。最近はたばこも辞めました。二十歳くらいからハイライトを1日で5箱吸っていましたがぱっと辞めて、いまはまったく吸わなくなりました。そうするとやっぱり、体調も良いですね。
ここ5、6年は、仕事がなければ早い時で7時にはベッドに入ります。 以前、俳優の哀川翔から「和泉監督、僕は8時前に寝ますよ」と言われましたけど、僕は哀川より早いですよね。
時々、夜7時に寝て、2時間後の夜9時頃に「うわ~っ、遅刻した」とびっくりして目が覚めたりもします。
Q布団派それともベッド派?
ベッドで寝ています。ロケに行ってもどこにいってもベッドでないと眠れません。寝床の高さがないと駄目なのかな。枕はウレタン素材でやや固めのものを使っています。
瘋癲(ふうてん)生活をしていた青年時代
Q映画監督になったきっかけを教えて下さい。
10代、20代の頃は腐るほど映画を観ました。最初にショックを受けた作品は『勝手にしやがれ』(1959年フランス映画/監督・脚本はジャン=リュック・ゴダール)でした。パリが舞台で、当時は絵描きになりたい気持ちも強かったからかもしれません。

いまのように情報が豊富な時代ではありませんからね。雑誌に掲載されたパリやフランスの記事は切り抜いてスクラップしていたような時代です。映画でパリが動いているシーン。世界最先端の流行都市、パリが動いている、という事にまず感動して衝撃を受けました。
ただ最初はそれほど、映画監督になりたいという強い意志はなかったですね。親父(*1)も彫刻をしたり舞台演出をしたり役者をしたり、テレビの制作会社をしたりと好き勝手に生きていましたけど、僕もかなり自由にやってきました。
京都の高校(現/京都外大西高等学校)を卒業してからは上京して新宿で暮らし始めました。新宿には当時、瘋癲(ふうてん/定職を持たずふらふらと町中をさまよっているような人)と呼ばれる人たちがいたんですけど、僕もその1人だったのかな。
当時ははっきりとした目標や夢があったわけではなくて、なんとなく好きな事をしている感じでした。真剣に映画監督になりたいと思っている人たちがいる中でぼくはちょっとどうかなと思うけど気が向くままに生きていたら映画監督になっていた感じですね。
Qでも、ただの瘋癲(ふうてん)ではプロの映画監督にはなれないと思います。
もちろんそんな簡単に映画監督になれるわけはないですよね、たしかに。僕は親父と同じように絵を描くことも好きでしたが、同じくらい物語を書く事も好きでした。
お金がなくなれば週刊誌で記事やちょっとしたエッセイを書いていました。そのうち、映画の脚本に興味を持ち始めました。でもシナリオ学校に通うお金はない。ならばと、まず一冊、シナリオの月刊誌を買って、それをまず、写経のように新聞紙に丸写ししました。
部屋は電気代が払えずに止められていたので、アパートの前にある新宿御苑の堀を乗り越えて、照明の下で夢中になって書き写しました。
書き写しながら「この話はどういう展開をしていくのだろうか」、「このキャラクターはどういう行動を起こすのか」「彼の気持ちはこれからどうなっていくのか」と考え続けました。
そうするとだんだんシナリオの書き方がわかってきてテクニックも身に付いた。そんな作業を繰り返すうち、オリジナルのストーリーを考えてみたいと思うようになりました。
思いを貫いて完成した映画『オン・ザ・ロード』
最初は成人映画の監督からスタートして、一般映画で監督デビューしたのは、30代半ばでした。『オン・ザ・ロード』という、白バイ警官が暴走を始める、という作品です。
脚本は自分で書き上げました。そうこうしていると、なぜか強い思いが伝わって友達が仲間になり、「これを映画にしようよ」という仲間が何人か集まってきて、実現に向けて動き始めました。

映画会社からは「じゃあきみもリスクを負いなさいよ。制作費を半分作ってごらん。そうしたらうちが半分、出してあげるから」と言われた。当時で7000万円の予算だったのかな。
「わかりました」と、答えたのは良いが、実際はお金なんてありませんでした。
でも思いだけはみな強烈に持っていた。朝方までどうすれば良いかを語り明かして、「暑いから窓を開けたら大金の入ったバックが飛び込んでこないかな」なんて話したりして(笑)。あとは「きみの実家、商売何かしていないの?」とか(笑)。
どうにか1000万円は集まった。でも半分の3500万円には全然足りない。でもある時、仲間と作った小さな事務所が原宿にあったのですが、原宿の街を誰かと会う約束をしていて歩いていると、フルーツパーラーの千疋屋の前で下駄の音が「カラン、カラン、カラン」と響いてきた。
振り返ると友人で芥川賞を受賞した高橋三千綱でした。
「和泉、おまえ偉い暗い顔して歩いているけど何やってんだ」 と聞かれた。僕は 「じつは映画を撮ろうと思って制作費を集めている。でもなかなかしんどくて、いまからもお金集めに行くんだ」 と話した。すると高橋は 「じゃあ俺も少し出すよ」 と言ってくれた。
ただ、彼は映画を撮るためにはどのくらいお金がかかるかは知らず、「100万、200万なら」という気持ちでいた。「あと2500万円足りない」と言うとびっくりしていました。
でもその時、ものすごく勇気付けられました。
「ひょっとしたら、いや絶対、『オン・ザ・ロード』は映像化できる』と。
それから本当に1週間もしないうちに、またかつての友人で、僕は勝手に瘋癲(ふうてん)と思い込んでいた相手が、実はある大きな会社の息子さんだった事がわかったり、「和泉が映画を撮りたいと言ってバタバタしているよ」と聞きつけて「じゃあみんなで協力しよう」なりお金を集める事が出来ました。
映画が完成して上映が決まってからも大変でした。成人映画から這い上がってきた監督なんて、まともには扱ってもらえなかった。マスコミ関係者もなかなか信用してくれない。記者会見の時は馬鹿にされたような質問が多かったですね。
「あなたはいままで100万、200万の成人映画と作ってきた。それが今度は7千万円ですか!? 映画のお金の使い方、わかりますか」と言った質問もあり、非常に悔しい思いをしました。
ただ当時は僕だけじゃなくて、成人映画から這い上がってきた監督はみなそういう目で見られていた。それを乗り越えて作品を作り、興行的にも成績を残して世間からようやく「やるじゃないか」と評価されました。
成人映画出身の監督は、いままでの映画とは違う発想で作品を作る人が多かった。それに興味を持たれて次の仕事も入ってきた。そうして何本か撮るようになって初めて自分が映画監督になったという実感を持てるようになりました。
『相棒』との出会い
東映で映画を撮った時のプロデューサーから「テレビの刑事ものなんですが、ちょっと読んでもらえませんか」と言われて渡されたのが、テレビ朝日系列の土曜ワイド劇場の単発ドラマとして企画された『相棒』の脚本でした。

読んだらこれが面白かった、「こういうスタイルの刑事ドラマもあるのか」と。それまでの刑事ドラマと言えば『大都会』や『西部警察』などアクションや男臭さ、『はぐれ刑事純情派』のような義理人情的な要素を押し出す作品が多かった。
でも『相棒』の脚本はまったく違うスタイルの刑事ドラマでした。警察官とその世界がリアルに垣間見える。拳銃を抜いて打ち合いをするシーンはありませんが、話の内容自体に深みがあって非常に面白い。脚本を読んでいるだけでわくわくしました。
監督を引き受ける上でもうひとつ決め手となったのは、主演に決まっていた水谷豊さんの存在です。豊さんとはそれ以前にテレビで違う作品を一緒に作りました。
それからある友人を介して食事をしたり、豊さんはお酒は飲めないですけど、お酒の席でお付き合いをして下さっていました。非常に懐が深い人で役者としてさまざまな面を持っている。「豊さんはこれまでにない刑事の姿をどう演じてくれるのか」と個人的にもすごく楽しみでした。

杉下右京のキャラクターも話し合って作り上げていきました。ロンドン帰りの刑事だったので、「豊さん、ちょっとオールバックにしません?」「眼鏡をかけて、ちょっと英国紳士風にいきましょうか」。「サスペンダーはどうでしょうかね」と、結構、ふたりで笑いながら作り上げました。
他の役も含めて、キャラクター設定はものすごく大事にしています。杉下右京の脇を固める役者さんには、小劇場出身の俳優さんを多く起用しました。小劇場で知名度はあっても、世間一般には馴染みの薄い俳優さんたち。ただ、非常に個性が強い。
「あっ、この人知ってる!」という俳優さんとはまったく違うお芝居が出来る事に僕は驚いて「おもしろいな~」と。
「だったら、こうしたらどうだろう」とか、いろいろなアイデアが出てきた。彼らもそれをおもしろがって「監督、本当に大丈夫ですか!? そんなことして」と。「いいじゃん、おもしろいからやろうよ」といろいろな冒険をした。最初の『相棒』はそうしてみんなでわいわいしながら作り上げました。
豊さんとは「これ、いままでの刑事ドラマにはない面白さがあるよね」「これは単発ドラマでは終わらない、きっと続くね」と話したことは覚えています。でもまさか13年も続くとは思いませんでした。
(次回後編は、和泉監督が思い描く『相棒』の最終回)